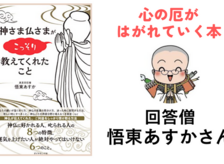15,000回、ただ隣にいた―hasunoha最多回答・東住職の10年
hasunoha回答僧・東(Azuma)住職の回答が10年で15,000件を超えました。
ただ隣にいる―その静かな姿勢が、どれだけ多くの人を支えてきたか。東住職の思いをhasunoha運営がお聞きしてきました。
----
スマホの画面に映る、知らない誰かの悩み。名前も顔も知らないその人に、そっと言葉を差し出す僧侶がいる。
栃木県佐野市のお寺の住職、東 好章(あずま・こうしょう)さん。hasunohaで、10年間にわたり、15,000件以上の声に耳を傾けてきた。
文章の先にいる誰かの苦しみに、静かに、でも確かに寄り添い続けるその姿に、私たちは何を見出すのだろうか。
その始まりは、ちょっと不思議な質問からだった。
幽霊のお坊さんと最初の回答
運営: hasunohaが始まったのは2012年でしたね。最初は5人のお坊さんからスタートして、その中に東さんもいらっしゃいました。
ただ、質問が届くようになっても、他の方々はすぐに回答される中で、東さんはしばらく様子を見ておられた印象があります。
東住職: (笑)そうですね。引いてました。様子を見てましたね、しばらく。
運営: 初めて回答されたのは、始まってから数か月か、1年くらい経った頃でしたね。 確か「幽霊は見えますか?」という質問への回答が印象的で……私の中では東さんは“幽霊のお坊さん”というイメージでした(笑)。
東住職: たしかに、あれは他のお坊さんでは答えにくい質問だったと思います。仏教的・論理的に考えると、幽霊のようなものは説明が難しい。科学と同じで、根拠をもって「あります」とは言いにくいんですよね。
でも、私は体験として“見えた”ことがあったんです。だからこれは、自分が答えたほうがいいだろうと思って書いたんですよ。当時は、他のお坊さんが答えづらい質問に対して、自分がオプション的に関われればいいかな、というスタンスでしたね。
東住職: それともうひとつ。 自死に関する悩み――「死にたい」という相談は特に多かったので、浦上さんと話して、できるだけ答えていこうと決めていました。 私も浦上さんも、「自死・自殺に向き合う僧侶の会」のメンバーですから。 そのあたりから、少しずつ回答が増えていったのかなと思います。
ネットで言葉を差し出すということ(リスクと覚悟)
東住職: 当時は、浦上さんや川口さん、丹下さんがとてもたくさん回答されていて、私も「できる範囲で少しずつ答えていこうかな」と思っていました。
そうしていくうちに、「あれ? 意外と回答ってできるもんなんだな」と思うようになって。続けていくことで、回答へのハードルが自然と下がっていったんです。
昨日も、ある学校で講演をしたのですが、子どもたちに「SNSに投稿するときは、一度文章を読み直してから投稿しましょう」と伝えました。そういう話を聞くと、やっぱり構えてしまうというか、投稿って重くなるんですよね。回答もしづらくなる。
できれば、自分の本心や考えをさらけ出したくない。それは私たち大人だから。しかも、私はお寺の僧侶、住職を務めています。だからこそ、言葉尻を捉えられて誹謗中傷されたり、非難されたりするのは絶対に避けたい。そういう気持ちも当然ありました。
一言一言、言葉を発するということは、リスクを伴います。だから最初の頃は、回答するのも簡単じゃなかった。でも、続けていくうちに、そのリスクへの恐れも少しずつ薄れてきたんです。
私、実はスマホで回答してるんですよ。スマホで相談文をスクロールして読んで、「こんな感じで書いてみようかな」と思ったら、そのまま「回答する」を押す。 最初の頃は、「この表現でいいかな?」「ちゃんと伝わるかな?」って何度も読み直して、校正してから投稿していました。
でも、あるときから、そこまで厳密にしなくてもいいんじゃないかって思えるようになって。もちろん、ある程度は気をつけますけど、「自己保身のために過剰に厳しくなる必要はない」と思えるようになってきた。
その感覚が、少しずつ「言葉を差し出すこと」への恐れを和らげてくれたんだと思います。

仏教者として、悩みに向き合うということ
東住職: 私、いつか自分の回答が炎上して、誹謗中傷を受ける覚悟はあります。でも、それよりも先に立つのは、「悩んで苦しんでいる人に、少しでも安心してもらいたい」という気持ちなんです。
悩んで、死にたいと思っている人。あるいは、愛する人との別れを経験して、後悔の中で苦しんでいる人。そういう方に対して、私は浄土宗の僧侶として伝えたい。
「仏様が必ず、極楽浄土でお救いくださいます。だから安心してください」と。
私自身、もともと人見知りなんです。あまり信じてもらえないですけど(笑)。 小学校は高学年になるにつれて、だんだん通えなくなりました。中学校も、半分くらいしか行っていません。
人前に立つと、頭が真っ白になって何も話せなくなる。 そんなトラウマもあるんです。だから、人前で話すのが怖い。
だからこそ、相談者さんと自分とに、境界線があるとは思っていません。同じ目線なんです。私は今でも、あの頃の劣等感を抱えたまま生きています。
自分の実体験の中で、「この人の気持ち、なんとなくわかる」と思えたときに、言葉が出てくる。そうでなければ、ただ上から目線で言ってるだけになってしまう。
救いを伝える責任と希望
東住職: 私たちがhasunohaでお答えしている内容って、正直、すぐに「はい、実践します!」っていう方は少ないと思うんです。むしろ、一度読んで、それで終わりじゃなくて、何度も読み返してくださる方が多いんじゃないかと感じています。
だから私は、「仏の救い」ということを、できるだけ伝えるようにしています。
仏様、神様、ご先祖様―― そうした存在が、必ず見守ってくださっている。必ずお救いくださる。
そうお伝えすることで、少しでも“安心を持ってもらえるなら、それが今を生きる力につながる。 私はそう信じているんです。
もちろん、「本当にそうなの?」って思う方もいらっしゃると思います。でも私は、僧侶として、その救いを語り続けたい。誰かの心が、少しでも軽くなってくれるなら。それが、私にとっての“回答を続ける理由のひとつです。

責めない。もう、本人が自分を責めているから
東住職: 「助けてください」「もう苦しい」「死にたい」―― そういう相談は、必ず読むようにしています。
最近特に感じるのは、罪の意識を強く持っている相談者が多いということです。たとえば不倫をしてしまった方、自分を責め続けている方。私は、そういう方をさらに追い込むような言い方は、できるだけしないようにしています。
そもそも、責めるのは自分自身なんですよね。もう、本人が自分のことを責めている。それにさらに私たちが乗っかって責めたら、その人はもう逃げ場がなくなってしまいます。
もちろん、反省は大切です。神仏に対して懺悔していただくようにお伝えすることもあります。でも、それは“諌める”というより、“促す”ということです。 反省の先に、救いがあるという視点で伝えたい。
ネットの中では、誰かが間違ったことをしたときに、すぐに“犯人扱い”されたり、攻撃されたりすることが多い。だからこそ、私は「責めない」という姿勢を大切にしています。
つながっていると感じられる瞬間
東住職: 私が回答の原動力になっているのは、やっぱり「相談者さんとつながっている」と感じられる瞬間です。
たとえば、お礼の返事がこないことも、正直よくあります。でも、三か月、半年たってから、突然返ってくることがあるんです。
「改めて読み直してみたら、ありがたかったです」って。そういう言葉をもらったとき、「ああ、この人、生きててくれたんだ」って、まずそれが嬉しいんですよね。
hasunohaには、自死や自殺の瀬戸際にいる方からの相談もたくさんあります。 そういう方に回答しても、「その後」がわからないことも多い。でも、しばらくしてから「生きてます」っていう一言が届いたとき。もう、それだけでありがたいと思えるんです。
お寺と社会をつなぐhasunoha
東住職: 今、私がhasunohaで回答していることって、そのまま「お寺の活動」だと思っているんです。
法事や法話の場でも、hasunohaのことを話すことがありますし、実際にカードを印刷して、参列者の方全員に配っています。 それも私にとっては、法務の一環なんです。
仏様は必ず救ってくださる。人生には、つらいことも苦しいこともある。 でも、そういうときにはお寺に相談してください―― 法事の場でも、私はいつもそう伝えています。
hasunohaと法務は、私の中ではリンクしています。
言い方はちょっと悪いかもしれませんが、それって「お寺の存続」にも関わってくることなんです。私が回答する。必要とされる。だから、お寺も必要とされる。
お寺は、人を導き、救う場所であるべきだと思うんです。 そんな活動をしているうちに、市役所や児童相談所といった行政機関とも自然とつながるようになっていきました。福祉仏教という言葉がありますけど、まさにそのかたちだと思います。
hasunohaでの回答を通じて様々なご縁もつながっています。相談者の方から「おきもち」の喜捨を頂いて、それを「おてらおやつクラブ」の活動資金にしながら地域のお菓子屋さんにも協力して頂いて、栃木県若年者支援機構のお子さん達などに多くのお菓子やお米等をお届けしています。
社会や地域と関わることで、お寺の「社会的な価値」や「存在理由」が強まっていく。それが、檀家さんとの新たなご縁にもつながっていくんです。 爆発的に増えるというわけではありませんが、うちのお寺、檀家さん少しずつ増えてるんですよ。 社会性のある活動をしているからこそ、いろんなつながりができて、そこから自然に「ぜひこのご住職に」と言っていただける。
hasunohaが当初立ち上がった時に井上広法さんから「ハスノハで回答することで、人とのつながりが増えて檀家が増えるということにつながってほしい」との思いを聞いた通り、檀家が増えていくことにもなりました。
活動そのものが、お寺の“利益(りやく)”になっているのを感じています。
人権・福祉の現場へ広がった対話
東住職: hasunohaを始めてから、自分自身にもいろんな変化がありました。
たとえば、人権擁護委員の仕事。そのお話をいただいたのも、hasunohaで回答僧侶をやっていたことがきっかけでした。民生委員や児童委員のお役目もそうです。子ども支援の活動にも、あとからどんどんつながっていった。
「hasunohaで人の悩みに耳を傾けてきた東さんなら、こういう立場でも活動してくれるだろう」 そう思ってくださったんだと思います。
だから私にとってhasunohaは、単なる“ネットでの活動”ではなくて、地域福祉の現場に橋をかけてくれた、大きな入り口だったとも言えるんです。

一向寺の「さのまる君」
誰にも話せないことがある人へ
東住職: 人に相談するって、簡単なことじゃないですよね。
正直、私自身も、「じゃあ自分の悩みをhasunohaに相談してみたら?」って言われたら…… たぶん、すぐにはできないと思います。相談って、それくらいハードルがあることなんです。
でも、自分ひとりで抱えているよりは、 たとえ少しでも誰かに聞いてもらえたら、 ほんのちょっとでも気分が変わることって、あると思うんです。
相談の文章を書くだけでも、少し気持ちが整理されていくこともあります。だから、気軽に書いてみてほしい。重く考えすぎずにね。
中には、「自分でも何を書いてるのかわからなくなってしまいました、乱文ですみません」そんな風に書かれる方もいらっしゃいます。でも、それでいいんですよ。迷ってる、悩んでる、自分でも整理できない―― そのままの気持ちを書き出すことで、少しずつ気持ちが動いていく。 そんな“変化のきっかけ”になることもあると思うんです。
仲間のお坊さんたちへ
お坊さんたちにも、こう伝えたいんです。 「気軽に回答してください」って。
いまの時代、ネットもありますし、AIだって出てきました。情報はどこにでもあって、答えも“自動で”返ってくるようになりました。でも、生身の人間として、 “いまこの瞬間の感覚で誰かに向き合う”ってことは、きっとこれからも大事なことだと思うんです。
私たち人間は、有限な存在です。できる期間にも、できることにも限りがある。
でも、その限られた中で、いま自分が感じたこと、経験してきたこと、心に引っかかったこと―― そういうものを、そのまま伝えるだけで、誰かの気持ちにふっと触れることがあると思うんです。
だから、完璧じゃなくてもいい。説法みたいな文章じゃなくてもいい。一言でも、その人を想って書いたものであれば、必ず届くものがある。私は、そう信じています。
答え続けること、それは「そばにいる」こと
エピローグ、取材を終えて。
15,000件の相談に、すべて一人の僧侶が答えてきた。その事実だけでも、きっと十分に尊い。けれど、東住職はこう語る。「答えを出しているつもりは、あまりないんです。ただ、一緒に考えているだけで」
誰かの苦しみに、正解を突きつけるのではなく、誰にも言えなかった気持ちの隣に、そっと腰を下ろすように。 そのままを受け止めて、「ここにいますよ」と伝えるように。それが、東住職が10年かけて、静かに選び続けてきた在り方だった。
文章の先にいる、顔の見えない誰かのことを、「その人も、昔の自分かもしれない」と思いながら―― あの日の劣等感を抱きしめながら―― 救いの言葉を届けている。
もしかしたら、救われてきたのは、東住職自身だったのかもしれない。
hasunohaは、ただの相談サイトではない。 それは、どこかにある「もうひとつの本堂」だ。
今日も誰かがそこに座り、今日も東住職は、静かに答えを紡ぐ。
「私は、ここにいますよ」と伝えるように。
Kousyo Kuuyo Azuma
栃木県佐野市
浄土宗・一向寺住職
不動産企業の管理職、ファイナンシャル・プランナーなど歴任した後、師僧を継いで一向寺第38世の住職に就任。
hasunohaでの回答、個別相談、お寺での法務を通して、人間関係や恋愛のお悩み、自殺願望、大切な方の死に直面した苦しみなど、あらゆる悩みに手を差し伸べ続けている。