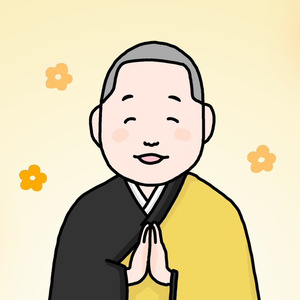夫の実家の新しいお仏壇のことです
今年、夫の父が亡くなりました。
義母は最初、義父は形式的なことを嫌っていたから、と言ってお仏壇も置くつもりもなくお葬式以降の法事もしない、と言っていました。
最初は私もびっくりしましたが、それもいいかなと思っていたら急にお仏壇を購入したり法事も予定立てていました。気持ちがいろいろ変るのです。
定年まで仕事をしていたのでお付き合いもあったでしょうし75歳ということもあり人生経験からいろいろ知っていると思っていましたがお仏壇は購入したらそのまま使いはじめたらいいと思っていたり、今回四十九日の法要がありましたが、喪服着用と知らなかったり、というような感じです。
そして、そのお仏壇なのですが、義母が選んだ場所は物置部屋です。いろんな物を置いていてご住職が来られてもかろうじて前に座っていただく場所がある程度の部屋です。
次に初盆があってそのときは私たち夫婦と弟夫婦も集まるのでそのときだけはリビングにお仏壇を移動させてセッティングすると言っています。義母は一人暮らしで他にも部屋はあるのにどうして物置部屋なのか考えていたら嫁の私でも腹が立ってくるくらいです。
夫に聞いても、「さぁ、母が決めたからいいのでは?」と他人事のように言うだけで弟夫婦も別に何も思っていない様子です。
置き場所のことで私のようにいろいろ考えることは必要のないことでしょうか?亡くなった義父の奥さんや息子たちが良しとしているなら嫁の私は口出しすることではないのでしょうか?お仏壇は物置にあってもいいものでしょうか?
お坊さんからの回答 2件
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
自分たちの都合を優先して扱っているうちは仏壇にはならない
残念ながら先祖・先亡・仏法僧の三宝・諸天善神を敬う気持ちがない家の仏壇はただの箱です。
これを機会に、あなただけでも神仏を敬う気持ちを強くなさってください。
変な表現ですが、まだ、本当の意味で家庭の中に仏様がいらしていないのだと言えます。
神仏とは、自分たちを存在たらしめている大いなる働きです。
自分の一部として見るべきものです。
その関係性をよく感じ取ってみてください。
亡き人をぞんざいに扱えば、生きている人をもぞんざいに扱うようになってゆくものです。
仏壇は家庭の中のお寺、みたまやです。
人がそこにいる、ということを忘れてはいけません。
敬いがなく、人間の都合だけで仏壇を取り扱っていれば、ただの箱扱いです。
それは、同時に自分たちをぞんざいに扱っている姿と言えます。
お母さんにとっては、そこは物置部屋とか、ぞんざいな場所という感覚がないだけかもしれません。「お母さん流」なのでしょう。
あなたはあなたで祖霊をしっかり敬ってください。
姿勢も心も大切です
とうこさん、はじめまして。
徳島県の法話と天井絵の寺 觀音寺 中村太釈です。
とうこさんの義父を見送られたとのこと。寂しくなられたことと存じます。
義母の仏壇に対する考え方が気になるのですね。私もとうこさんと同感です。
お仏壇は、故人の生前を思い起こすためにお供えをして香を焚き(線香を灯し)、ロウソクと花を供えて手を合わせる場所です。家の中で、どのような場所が故人を思い起こすには最も適切でしょうか。
お儀母さまにも、亡き夫を毎日思い起こすことができることができるよう祈念しております。
質問者からのお礼
ありがとうございます。
実は、お仏壇を購入したと聞いたときに「開眼法要はいつですか?」と私が聞いてみたらそこで初めてそういうことが必要と義母は知り、自宅でご住職に来ていただき済ませています。
でも、お花はこれでもかというくらいに飾っているわりにはお供えのご飯は数日に一回、という中途半端なことをしていて、「お仏壇を置いている」というまさに箱のような感じです。



 お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00
お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00