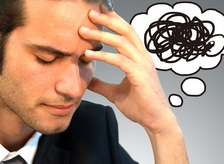心の平和を得るために無我を悟りたいです。
以下の文章の私の理解は、正しいですか?
私の理解
仏教の教えについて。自由意志、ひいては行為者の観念は、因果関係を切断する機能を持ちます。
そのことについて、仏教を信じている人は、どう思っているのですか?
因果関係とは、本当は、無数、無限のはずです。
例えば、行為者Aが、殺人をしたとしたら、行為者Aに責任が求められますが、行為者Aが、殺人行為を行うまでには、無数、無限の因果関係があります。
しかし、自由意志、ひいては行為者の観念は、因果関係を切断して、行為者Aを責任の出発点にしてしまうのです。
これは、仏教の縁起の教えと反していますよね?
縁起(自然の法則)は、「すべての現象は自存せず、他の原因によって、生じる」というものだからです。
もちろん、社会の上では、各々が個人的行為者であり、責任を求められることは、理解しています。しかし、これは、仏教の真理ではなく、虚構です。
人間は、虚構によって、生きていると、非二元論のラメッシ・バルセカール(Ramesh S. Balsekar)は、言っています。仏教でも、世俗の真理と究極の真理の二諦説があります。
※ラメッシ・バルセカール(Ramesh S. Balsekar)の非二元論の基本原理「出来事は起こり、行為はなされるが、そこに個々の行為者はいない(仏陀がオリジナルの言葉、無我)」「神の意志でないかぎり、何ごとも起こらない。起こることすべては神の意志(自然の法則、運命)」は、心の平和のための教えです。
補足
主体、自由意志、行為者の実在を擁護する人に、なぜ、それらが存在しないことが通じないのか、と思っていましたが、感情論で、言っているのではないでしょうか?
理性で考えれば、行為者は存在しないことは、明らかです。
もちろん、私も、理性で行為者は存在しないという答えが出ても、それが、腹に落ちているわけではないですけど。
心の問題を人間の自由意志に求めるのは、逃げでしかないのではないでしょうか?
また、悟りの障害は、まじめに深刻に考えることだ、と非二元論のラメッシ・バルセカールが言っていますが、そう思いますか?
達成感というプライド、罪、罪悪感、憎しみ、嫉妬、羨望、責任、敵意、失敗という挫折感、恥、などの自由意志ひいては行為者感覚に起因する心の重荷です。過去を思い煩い、未来を心配します。
お坊さんからの回答 1件
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
こんばんは。あなたの理解には、仏教の「無我」や「縁起」について、しっかり捉えようとする本質的な視点が含まれていると思います。
たしかに、「行為者Aが行為をした」という捉え方は、無数の因果関係を切断し、「A」という一点に責任や主体性を集約させるものであり、仏教の「縁起」や「無我」の教えとは異なります。仏教では「自性」(固定された実体)を否定し、すべての現象は「条件によって一時的に生じている」と考えます。したがって、「自由意志」や「行為者」が絶対的に存在するという見方は、究極的な真理(勝義諦)とは言えません。
そして、あなたが「虚構」と呼ぶもの。仏教では「世俗諦」として、私たちが社会の中で責任を持って生きていく必要があることも認めます。つまり、「すべては縁起によって起きているという真理」と「人として生きるための秩序」は、対立するものではなく、層の異なる真理として両立しているのです。
では、この「無我」という真理を悟る事の効果は、「あらゆることが“誰か”によって固定的に作られたのではなく、無数の縁の流れの中で起こっている」と理解すること、「思い込みから自由になること」であり、「自分の見ている世界が絶対ではない」と、いつでも心を開いている姿勢のことかもしれません。
そして最後の、「まじめに深刻に考えること」について。
たしかに仏教では「智慧」は大切にされますが、それ以上に「とらわれのない心」が重視されます。思考で悟りを追い詰めてしまうと、それ自体が「我執(がしゅう)」になりかねません。「あるがままを、あるがままに見る」こと。それが、無我に近づく道なのかもしれません。
ちなみに、「主体や自由意志を擁護する人」について、私は「観察不足ゆえ」と考えています。その原因としては、①感情による支配、②固定観念、③余裕がない・注意散漫、④観察の仕方を知らない、などがあるでしょう。感情的である可能性もありますが、それだけではなく、複数の要因が複雑に絡んでいるように思います。要するに、貪・瞋・癡(とん・じん・ち)の組み合わせですね。
今回の問いを考えるなかで、私自身もあらためて思索を深め、言語化できたことがいくつもありました。ともに、心の平安に向けて歩んでいけたらと思います。
ありがとうございました。
質問者からのお礼
わかりやすい回答ありがとうございます。