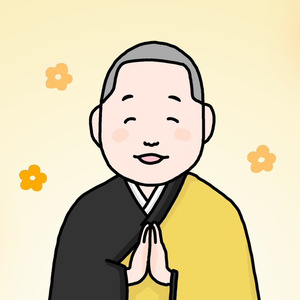お坊さんからの回答 3件
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
守って下さる方々をさらに世に広めるためにも神仏の外護者となる
あなたのような素晴らしい感性に目覚めるまでは、人間とは、ずっとエゴのカタマリを生き続けてしまうものなのです。私自身もかつてはそうでした。
そのエゴや自分勝手の思い上がりに気づいて、それを慎むことが世の中全体の平安に協力する事になると知れば、そういう心を広めることこそ、あなたを守って下さった方々が一番お喜びになることです、。
お寺や神社とは、分りやすく申し上げれば、そういう心の善玉菌を増やすべく活動をしている所なのです。
ところが、場所場所によっては、運営も困難です。
ここも無料で勤めておりますが実質、経済的にも大変です。
どうか、神仏をうやまう気持ちをさらにもって、神仏の心を広めるべく、お寺や神社などを外護するようにお勤めください。
ここで私が申し上げていることも、もともと私のものではありません。
すべては天地自然、神仏からの授かりものです。
授かり物は世の中に何らかの形でお返しし、神仏によって救われた人は神仏を敬って授かった知恵や力や財をすべて自分の為に使うべきではありません。
出来る範囲で構いませんから、世間に役に立てていただけるように行動や広報や布施などで貢献をなさってください。
宗教なんぞ要らん、とお寺や神社を壊すエゴ・自我のカタマリのような人が増えてきています。
お寺や神社が存続していけるように、何らかの形で援助、外護をして頂けるとありがたい
手を合わせること
やすさん、はじめまして。質問を拝読いたしました。
やすさんを守ってくださる存在、例えば神仏などに対してどのように感謝の意を表せばよいのか分からないのですね。
やすさんは、ただ手を合わせるだけでよいと思います。
仏教では「相互供養 相互礼拝」と説きます。互いに認め合い、互いに慈しみ合うことを指しています。
慈しみの心を神仏に向け、同じようにやすさん以外の誰かに慈しみの心を向けてください。
信仰心
無心に手を合わせて下さい。
時には感謝の言葉をいいながら、生きていることへの有難さを感じ、お賽銭を入れたくなれば入れればいい。
道端にあるお地蔵さんや道祖神へも手を合わせ。
ふらっと立ち寄った無人のお寺で本尊に手を合わせ、蝉の声に耳を傾ける。
車で参拝して、変なとこへ車を止めて、住職に怒られたり。
神仏への信仰が、生活の一部として存在しております。
感謝は自然に起こるものです。
質問者からのお礼
御坊様、ありがとうございます。私は日ごろ辛く、いてくださり、訪れる、霊のような、方々と、ともに暮らし,病みの、回復を、行ってます。地元の、名刹に、足が、くたびれるまで、足を運んではどうか、など、。そのよう心がけます。
ご回答、ありがとうございます。
日々修行と心がけて、今年も生きていきます。



 お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00
お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00