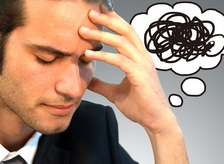父を理解するべきなのでしょうか
初めまして、花火と申します。
私は幼少期に母を病気で亡くし、そこから父と兄2人で生活してきました。
ですが、兄は2人ともやむを得ず自己破産をしなければならないほど借金をし、1人に至っては逮捕されています。
母方の親戚が父を責め(勿論病気は自然の摂理なのでどうしようもないことです)、兄達も仲間に加わったため父は心を病みました。
そんな家庭環境の中、父が怒鳴ることは仕方の無いことだと思っていました。
お恥ずかしい話ですが、私も一度だけ家出をしたり学校を長期間休んだ過去があります。
そのため父に迷惑をかけすぎている自覚があり、罪悪感に苛まれ父から怒鳴られることを致し方ないことだと思っていました。
それでも夜ご飯は時間をずらさないと空気が悪くて食べられるようなもので無かったり、だんだん外に出るのが億劫になったり、突然不安になったり、感情の抑制が最近は効きません。
父を理解しようと思っても、「母が死んで嬉しそうに見える」「悲劇のヒロインだな」と言われたことや、友達と遊ぶと言っただけで「どうせ金遣いのあらい子なんだろ」、地元に戻れば「ここが大嫌い」、兄の話になれば「死にたい」「なんでこんなに辛いんだ」「母さんは先に死ねてよかった」、書ききれないほど言われたことが頭をぐるぐる巡ります。
その割に私の自慢をしたり、都合良く褒めたり、たまにこの人の宣伝道具しかないのではと思うことがあります。
私は亡くなっても母親のことが大好きなので、聞くのが本当に辛いです。苦しくて仕方ありません。
諸事情で1ヶ月も経たない内に家を出ます、色々なことがあっても父を理解するべきなのでしょうか。大変漠然とした質問で恐縮なのですが、お答え頂ければ幸いです。
お坊さんからの回答 2件
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
今は理解できなくても
こんにちは。
あなたが「色々なことがあっても父を理解するべき」と思い悩んでいるということは、少なくとも「理解するべき」何かがあると思っているからではないしょうか。
他の質問で、最初から毒親であるという結論から始めている質問がありますが、あなたの場合はそうでありません。
自分の親として受け入れられない部分も多々あるが、本当は受け入れたい或いは整理しきれない部分がない混ぜになっている、そういう印象を持ちます。
「幼少期に母を病気で亡くし、そこから父と兄2人で生活」が始まって以降は相当複雑な経緯があるようです。
あなたは、文面の多くを割いてお父さんからの「書ききれないほど言われたこと」、或いは他者に向けられた「宣伝道具」のような扱いを受けていること、「大好き」な亡き「母親のこと」を傷つける発言をすることに注目しています。そこだけを読めば、何と無神経で酷い父親だろうという見方もできるかもしれません。
しかし、一方でお父さんは「心を病」むほどに「母方の親戚」と息子二人から、お母さんの病死について「責め」られたようです。その病がお父さんと何らかの関係があって「責め」られたか、そこは書かれていないため分かりません。
でも、「病気は自然の摂理なのでどうしようもないこと」とあなたが書いているということは、恐らく「責め」ること事自体に不当さがあったのでしょう。お母さんが若くして亡くなった悲しみを、周囲と息子さんがお父さんを責めることで半ば八つ当たりをしたのかもしれません。
そして、お父さんはお母さん亡きあと、あなたを含めて3人の子どもを育てなければいけなかった。それは経済的に、心身の負担からいっても大変な負担だったでしょう。しかも、その生活は息子二人から不当に「責め」られる生活です。
お父さんがそんな生活で、「怒鳴る」という爆発した表現でしか自分を表せなかった。それは当然不適切であるけれども、またあなたにとって不本意だったとは思うけれども、一人の孤独な人間として、辛酸極まる生活の中で出さざるを得ない叫びだったとも見えるのです。
今あなたが「家を出」るというのは当事者としてやむを得ないし、賢明な判断であるとも思います。ただ、今は理解できなくても、後になって理解できることがあるのかもしれない、そういう余地を残して頂けたら、と思いました(字数制限)
🍚作られた人間心理はその後も作り替えることも可能🍙🍛
たとえば1チャンネルしか映らないテレビを毎日見ている人はそこで流れる情報しかしりませんし、それが真実だと思うようになるものです。
私はおボーサンの世界に長年居ましたが、いじめやハラスメントも沢山見てきました。僧侶の世界なのになぜこんなことが?もちろん立派な人も沢山いますが、立場が上の人で心の病んだ人が一人いるだけで周りは本当に迷惑しました。
私は曲がったことが嫌いだったものですから、先輩だろうが後輩だろうが人間は人間性だと思っておりますので、立場を気にせず後輩いじめをするその相手に対して朝の会議でそういうことはやめてくださいと申しあげましたら、そのタヌキちゃんは「なんでみんなの前でいうんですか?」と加害者の癖に責任転嫁。坊さんとは坊さんになったから坊さんなのではない。立派なお寺があるからお寺なのでもなく、立場が偉いから偉いのでもない。その人の今の心理状態がどうであるかこそすべてだと確信しました。悟りを得ようが三年前に開いた悟りを掴んでエラそーにして人生全ステージクリアしたわいというような態度をとっている人は別の意味で終わっていると感じました。世の中、いつ終わったなんてことがありましょうか?
お父さんは生まれてから親からのDVもあったかもしれない、ハラスメントもあったかもしれない、学校や職場、男の競争社会でひどい目に合わされたかもしれない。その結果が負の伝播、負の感染、負の共有、負の維持で今に至っている。
自分で自分を浄化も向上も救済もできない心理に陥っているかもしれない。
そうでなければ口を開けばネガティブな人になんてならないよ。この世でそういう因果関係なしに元々、性格悪い人なんて存在すらしないのです。
よって、おとーさんの心にはぐっさりと毒が刺さっている状態だと思います。あなたがコントロールや牽引ができる親子関係であるなら上手に善導してあげればいいでしょうが、人は親子でも変えられない。
だから、父親に高い人間性を要求はしないこと。あなたが変えられないことで病むから。ご飯やパンというものはそのまま食べてもいいですが、縁をとっぴん具することで変わる。どうすればもっと美味しくなるのか。食事のたびに考えてごらん。お父さんはもっと美味しくなるかも?みたく。変わっていく方法がある。過去はどうでもこれからは可変可能。まずはノリでもまいてみよう、褒めふりかけかけてみようとか。🍙



 応談できる時間帯は、その日によって違いますのでお確かめ下さい。
月曜日〜金曜日(祝日除く)13時〜21時
土曜、日曜、祝日 18時〜21時
お盆(8月1日〜15日)、お彼岸は対応できません。
応談できる時間帯は、その日によって違いますのでお確かめ下さい。
月曜日〜金曜日(祝日除く)13時〜21時
土曜、日曜、祝日 18時〜21時
お盆(8月1日〜15日)、お彼岸は対応できません。