日本の僧侶と中国の僧侶の違い
日本の仏教と中国の仏教は深い絆があります。
長い時間を経て、両国の僧侶の生活習慣はどんな違いがありますか?
お坊さんはどう思いますか?
どうぞよろしくお願いいたします!
中国の日本語専門大学生です。
お坊さんからの回答 2件
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
生活習慣の違い
KOUさん、はじめまして。
徳島県の法話と天井絵の寺 觀音寺 中村太釈です。
海外から質問をありがとうございます。
日本と中国の生活習慣の違いについて私の知っている範囲で書いておきます。
本堂の形や食事の仕方で違いがあります。中国は日本の畳文化がないので本堂に限らず殆どのお堂が土間敷で直立してお経を詠みます。日本は畳の上で座って今日を唱えます。食事も中国は土間なのでテーブルと椅子を使って食べます。日本では畳の上で座って食べます。
畳文化の違いで経を唱える時の姿勢や食事の様子も変わるようです。
みんな違って、みんなイイ。…ですが
昔、世界中の人たちが表面的な違いを乗り越えて仲良くなってもらいたいと思い、こんな歌を作りました。
「うどんも、ちじみも、パスタも、パンも、ナンも、素材はみんな麦。みんな違ってみなウマい。みんな違ってみんなイイ。」です。
ちょっと金子みすずさんの歌も若干パクりましたが(笑)。
宗教も、国の違い、生活習慣の違いも、みんな表面的に形が違っていても、根底が同じであるということを知っていればいいのではないでしょうか。
根底は、見る、聴く、話す、食べる、働く、あそぶ、幸せを求める…、世界民族共通です。
日本でも、宗派が変われば作法もみな違います。
同じ宗派ですら、人はみな違うものです。
表面的な違いよりも、同じ仏教として共通するべき事をこそ、隔ててはいけないと感じています。
(答えになっていませんが)
仏教は、人間のルールに縛られない生き方であるのにもかかわらず、現在の中国では、人間のルールによって、拘束制約されている面があるように中国に行った際に感じました。
人間は、一人一人、それぞれ固有の種です。それぞれ違った花を咲かせます。それぞれ一人一人が、その花を咲かせることだけに一生懸命になればいいと感じました。あれ、どこかで聞いたフレーズ?(笑)
曹洞宗では道元禅師が如浄禅師との出会いによって国境、歴史、民俗を超えて確かなる仏心、悟りが相承されました。
悟りには、表面的な呼び名が色々あって異なりますが、おなじ一心です。
そこが共通している事が一番大切であると思います。


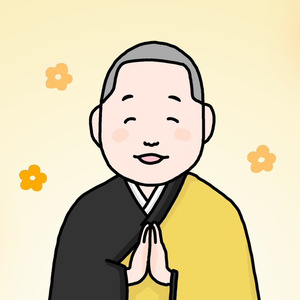

 お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00
お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00




