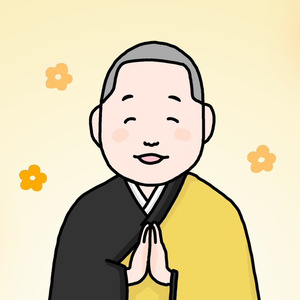愛する人を亡くしました
愛する人を亡くしました。
進行の早い病気で、でも希望を捨てたくなかったので、治療がうまくいく前提でしか話をしていませんでしたが、結局は…。
こんなことになるなら、もっと彼に対する感謝の気持ちを伝えたかったという後悔の思いばかりです。
私は、魂とか輪廻転生というようなことを信じています。
人は亡くなった後、49日までは魂がこの世にいるのですよね。だとしたら彼の魂は家族のところにいるのでしょうか?
私は彼の家族ではありません。
彼は天国に行けるでしょうか。
家族を大切にしている人でしたが裏切っていたことには変わりないので、それは“悪いこと”であり、天国には行けないのでしょうか…。
また、愛する人の死を“乗り越える”とはどういうことなのでしょうか。
彼が亡くなって以来、頭ではわかっているものの、気持ちがついていけません。それでも私は普通の生活を送るしかなく、自分は何をしているのだろうという気持ちになったりして、どうしたらいいのかわかりません。
お坊さんからの回答 2件
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
愛別離苦の解脱法
愛する人の死を乗り越えるとは、愛する人に対する心の執着がなくなることです。
仏教では愛別離苦と言いまして、愛する人との別れの苦しみを言います。
愛する人というのはもともとは他人様なのです。
たまたま、縁があってあなたという人を認めてくれたり、価値観が近かったり、褒めてくれたり好意を持ってくれたり、一緒に居てなんか気楽だったり心地よかったりで、総じて人間は「愛着」が生じます。
スキ、愛してる、君が欲しい、まぁもぉりたぁい(ニベア風に)。
全然知らない人から「守りたい」言われても、へ?と思うものです。
そもそもが、人間は誰のものでもなかったということをよくよく思いを巡らす必要があります。
天国に行っていないのはあなたのこころでしょう。
厳密にはあなたとその人との間の「禁断な」感じや後ろめたさが天国、極楽、安楽しないのです。
こういっちゃなんですが、好きになったという気持ちはホンモノでしょう。
それをあなたは完全肯定できないから苦しいだけです。
あなたに旦那がいようが、好きになってしまったはなってしまった。
ですが、好きや愛しているということの本当の理由に向き合うことの方が大切です。
苦しいときにちょっと優しい言葉をかけられたくらいで人って他人を好きになってしまったりするものです。それって、その人を好きというより、自分を好きでいてくれるその人が好きという条件付け付きだったりします。
本当に輪廻転生するなら、今すぐあなたも輪廻転生することです。
それは現代的には、この身心が前のことを残さずに彼が死んだ後も、今日は今日で新しい風を浴びているということ。あなたも良い意味で輪廻転生して、一瞬一瞬解脱しているのです。
49日も過ぎれば、あなたと彼の関係も執着のあり方も変わり、文字通り生まれ変わった関係が始まる。
いまだってもう生まれ変わった関係でしょう。
死後の世界の生まれ変わりというものは思想的な面があります。
そういう世界があると信じるならば、そういうものを追うのもよいでしょうが、人間はファンタジーでは救われません。
それよりもこの世界であなたが、彼とのかかわりのあり方において生まれ変わり続けていけばよいのです。
成仏とは一瞬一瞬の様子。
瞬時瞬時、われわれは無限に変化しています。
彼に対する今の思いはもう先程の彼に対する思いではないことをよくみるべきです。
死を乗りこえる4つのステージ
yuiさん、はじめまして。質問を拝読しました。
”愛する人の死を乗りこえる”ことについて書いておきます。
それ以外のことについては、今回は触れないでおきます。
悲嘆ケアといい、大切な人を亡くした後に心のケアを必要とすることがあります。喪失があまりに大きすぎると心のバランスを崩してしまうことがあるからです。
”愛する人の死を乗りこえる”ために必ず4つのステージをたどっていきます。
1.空白
悲しみという感情がスッポリと抜け落ちてしまい、空白のような状態になります。
「悲しいはずなのに涙が出ない」と考え込んでしまうこともありますが、喪失が大きくて心が壊れないようにブロックしているだけです。
2.落ち込み
空白の時期を過ぎて、少しずつ現実と直面します。この時、感情が大きく振れることがあります。突然に泣き出したり、怒り出したりします。深い谷底へ落ちていくような感覚にとらわれることもあります。
3.受け入れ
この段階でやっと喪失の悲しみを受け入れることができます。仏教では諸行無常と説きます。川上(かわかみ)から流れてきた水は川下(かわしも)へと流れていきます。川下の水は再び川上へと流れていくことはありません。
人の死も同じです。亡くなった人は還ってこないのです。
4.思い出
喪失の悲しみを受け入れていくことができれば、大切な人の死を思い出としていくことができるようになります。いつまでも故人を忘れることなく、供養していくことができるようになります。
それぞれの段階は、どれぐらいの時間がかかるのかは人それぞれです。
ですが、4つのステージをたどっていくことは変わりません。
知識として知っておいてくだされば幸いです。
質問者からのお礼
ありがとうございます。
私は生きているのだから前を向かなければいけませんね。
2件目のご回答の4つのステップの内、1と2を経験しました。あとは3と4がやってくるのですね。
いずれにしてももう少し時間が必要ですが、ご回答いただいたことを心にとめてがんばります。



 お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00
お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00