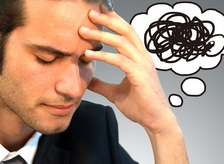悲しみから離れたいです。
芸術系の大学に通う18才です。
ここ数年私は自分の感情がよく分からなくなってしまいます。
もともと不注意が多くとても不器用な方です。
注意を受けたり、叱られたりした時
作品が思うように行かない時
やる気が微塵も起きないとに何か強制される時
そんな時、寂しい悲しいとかマイナスに感じるのは誰も同じだと思うので私は落ち込んでも大丈夫すぐ復活してこう、と切り替えるようにしています。
ですがどうもうまく行きません。切り替えて本を読んだり歌を歌ったりするのですがいつも最終的に吐くまで泣いて残るのは後悔や嫌悪感だけです。
このままでは、しなきゃいけない事は疎かしたい事も出来なくなってしまいそうです。
私はそれが怖いのです。
どうすれば悲しみや恐怖をとうざけることができるのでしょうか?
是非回答よろしくお願いいたします
他人の努力に嫉妬、周りと比較してしまう、どれだけやっても進まない
お坊さんからの回答 2件
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
作品の本質
あなたはアーティスト。
芸術を極める為にはまず、自分の心を添える前の姿を見ることが大切です。
あなたはものを見るにせよ、思うにせよそこに自分の思いを添えすぎている。
悩んで苦しんでいる時は何をやっていますか。
思いの世界であれやこれやと想像して苦しみを増している。
自分の思いこそが自分を苦しめていることを知るとよいでしょう。
その目が無ければ芸術の世界でも大成できません。
思想、思考の虜だからです。
芸術を見るにしても物事を思索するにしても、自分の自我の思いをつけ足さないままに処する、見る、過ごすことがあなたが救われるための道です。
どんな芸術作品でもいい。
どんな思いでもいい。
出てきた直後あなたはそのアートをあなたの独自の思いでペイントしてしまっている。
自分も思いも作品も損ねてしまっているのです。
自分の思いでペイントしていることに気づきましょう。
「自分が一番知っている」と同時に「自分が一番知らない」
芸術系の学校に通われているとのことで日々勉強しなければいけない内容が増え続けたり技術の向上に一所懸命精進しておられるのだと思います
私も不注意が多く不器用ですので昔からそれを理由に叱られることが多く凹んでしまうことがよくありました、昔だけでなく今も、ですが苦笑
自分自身の心というのは欲望や怒り、悲しみなど湧き上がるときは感情的になり比較的すぐ分かりますがそれを収めようとするとどうすればいいか分からない、どうにも収めるところがない状況に陥ることがよくあります
ちもよさんは落ち込んでもすぐに復活していこうと切り替えるようにしている、それは決して簡単なことではないのにも関わらず「切り替えられるようになる努力をしている」というのは非常に立派なことだと私は思います。
で、あるならば悲しいときは泣いたって構わないと私は思います。収めるところのない悲しみなら声に出して涙を流してある程度外に出してしまって減ってきたあたりで切り替えてみてはいかがでしょうか?
佛教では八つの逃れられない苦しみの一つに五蘊盛苦(ごうんじょうく)という苦しみがあり、どうにもならない心の苦しみ、自分の感情をコントロール出来ない苦しみがあるとされています。
ちもよさんが悲しみに対して苦しんでいることは何もおかしなことではなくちもよさんも、そして私も苦しみの中に居るのです。
ですから、「遠ざけなければいけない」と思うのではなく「上手に付き合っていく」ことを目指してみてはいかがでしょうか?
心理学の話になりますが「エモーショナル・ディスクロージャー」という手法がありまして、悲しみや怒りなどのマイナスの感情をひたすら紙に書き出す、どんどんどんどん紙にただ書き続ける、物足りなければ口でも言いながら書き出す、という解決法です。
これを実行した人としなかった人の復活スピードを実験したところ、前者のほうが「復活が早かった」、という実験結果があります。
まだまだこれからが感情と上手に付き合っていくことを勉強する時間ですので、焦り過ぎず気負い過ぎず少しずつ涙を流す時間を1秒でも短くしよう、くらいの気持ちで過ごしてみてはいかがでしょうか
少しでもちもよさんの悲しみが安らぐことを願って 合掌



 お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00
お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00