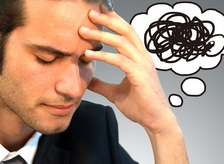おどおどしてしまうのを治したい
上司におどおどするのを治すように言われています。
テキパキ、元気いっぱい、自信満々なみんなを引っ張るリーダー(リーダーシップ)を目指したこともありましたが、無理しすぎて疲れて挫折しました。
私はおとなしめで、不器用、テンパりやすく、自信がなく、そして他人を陰で支えるのが好きなタイプです。
それを補うために必死に勉強して、資格を取ったり、通信講座をしたりしています。
上司には実力も経験もあるんだから、自信を持っておどおどするのを治してと言われます。
個人的にはおどおどしているつもりはないのですが、そう見えてしまうようです。
よくわかりませんが、自信がとにかくありません。
これは性格かなとも思います。
なのでおどおどするのだと思っています。
なにより、上司におどおどしないでと言われるのが辛いです。
どうしたら、おどおどするのを治せるのでしょうか?
お坊さんからの回答 2件
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
その場で答えを出さない
おどおどするときって、焦っているときや、目の前の出来事に思考スピードが追いつかないときではないでしょうか。
私もそういうことはよくあります。
まずは、その場で判断・即答しないで良いと考えてみてはどうでしょうか。
「ちょっと今は判断できないので、後で落ち着いて考えますね」と、堂々と言うのです。
自分が最前線のプレイヤーであったとしても、監督のようにドッシリ構えて眺めておきましょう。
そうして、良いアイデアが浮かぶのを待つのです。
また、作業をするときには、二つ先の作業予定を考えながら動きましょう。
目の前の作業を速くやりたい欲を抑えて、たとえ作業スピードが落ちてでも二つ先の計画を考えることを優先するくらいの気持ちで仕事しましょう。
その方が、トータルの作業時間は節約できる可能性もあります。
速さより早さ、早さより効率を考えましょう。
おどおどしながらでもいい結果は出せます
いきなりおどおどやきょときょとは治せませんが、脳が「なるほどこのようなものか」と認識して全体像を把握すればおどおどすることもキョトることもすぐ瞬時になくなります。そのためにも自分が「よくわからん」ということをなくす。わからないから人は恐怖や不安が生ずるだけの事。
うちには目の見えないドンという犬がいました。
生まれながらに目が開かず散歩の際にも門の一段高くなっているところにいつも鼻先をぶつけてしまって可哀そうでした。
ドンは雷が鳴ると何が起こっているかわからんもんですから、ガタガタブルブル震えるのでした。母が大丈夫だよ、大丈夫だよと安心させてあげていました。寒い時は家の中に入れてあげるとうれションをしたりで、若かった私はヒーと思いましたが、亡くなってしまいその思い出も今では誰かの悲しみや苦しみを導く作用になってくれているのだと思います。申し上げたいことは、おどおどを無くすということではなく、人前でしゃべる際でも脳がその場所がどういう所なのかをわかれば自然に緊張が無くなるように「よく見ろ」「よく知れ」「よく状況を把握せよ」ということです。実際にそうではないのに、過剰に心配しているところがあるでしょう。
それは事実以上の自分の妄想です。大丈夫です、刺された、殴られた、市中引き回しにされたなんてこともありませんでした。なにかあなたにとって失いたくないことや最悪の事態を想定しているところがあるのかもしれません。
ダイジョウブです。それでも平気でいる人がいるのですから何とかなるのです。
失う前にあれこれ考えすぎて過剰に心配する必要はありません。
それよりもなによりも、毎日仕事仕事と言ってもおおよそやることは決まっているはずでしょう。だから、何をやるにしても何に向かうにしても自分の恐怖や不安やおどおど、きょときょとを無くす最短ルートはそのことに関して自分がこわくならなくなるまで熟知するということです。
お釈迦様や覚者、如来の十の呼び名の一つに世間解という呼び名があります。
世の中のことをよく知る人と言う意味でもありますが、まず何より自分自身を正しく知ることです。心の道理を正しく知ることです。恐怖のメカニズムも正しく知ることです。やるべきことの具体停な内容を正しく知ることです。
わからないからこわいのですから、わかることでおどおどもすぐにおさまるでしょう。
質問者からのお礼
コメントをいただきありがとうございました。
2つ先を読みつつ、自分自身のことを見つめ治していこうと思います




 お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00
お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00