知的・精神障害者と仏教
先日の身体的弱者と出家の質問を書いていてふと思ったのですが、
重度の知的障害者というのは仏教のなかではどの位置にあるのでしょう。
重度の精神・知的障害者の方たちが僧職にはつけないことは理解できますが、仏教というものを私達の言葉・ものさしでは理解・表現できない、身体的・精神的に障害があるひとたちは、仏教徒にはなりえるのでしょうか。
仏教によって、例えば先ほどの浄土真宗の死後成仏し救われるといったような仏道の道というのは彼らにも開いているのでしょうか。
お坊さんからの回答 4件
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
障がい者は心で感じています
マイカさん、はじめまして。
徳島県の法話と天井絵の寺 觀音寺 中村太釈です。
重度の精神・知的障害者は私たちと違うものさしで考えているので、仏教ととなり得るのか?という質問ですね。
私の二男坊は中程度~重度の自閉症児です。
確かに彼は私と違うものさしで物事を捉え、考え、感じています。しかし、私よりもよほど純粋に仏教を捉えているような気がします。
二男坊は発語が少なく、自分の思っていることを十分に表現できませんが、雰囲気で仏教を感じているようです。
私たちは、言葉や仏像などの形で仏教を理解しようとします。しかし、二男坊はお寺の雰囲気や居心地で仏教を理解しています。仏教は宗派を問わず「安心」を説きます。お寺は心安まるところであり、心を浄化するところです。それを二男坊は感覚的に分かっているような気がします。
障がい者と私たちは捉え方が違いますが、感じていることは同じです。
仏教を感じて心で受け入れていくことができるので、成仏への道も開かれていると思います。
障害は僧侶が決めるものではない。
こんにちは。
知的障害と仏教、、、
私がよく聞く話だと阿弥陀経という経典に出てくる周利槃陀伽(しゅりはんだか)というお坊さんのエピソードがあります。
経典を覚えられない物覚えの悪さがありお坊さんを辞めたいと申し出たようですが、お釈迦様に経典はいいからあなたは掃除をしっかりしなさいと言われて、掃除を長年の間コツコツひたむきに行じたところ、他の僧侶からも一目おかれる釈迦の高弟になったそうです。
ほかにも、障害の有無は弥陀の救いの要件にならないようなことが経典か歴代の僧侶の注釈書に書いてあった気がするので確認します。
余談ですが、障害という概念。
WHOが国際障害分類から国際生活機能分類にアップデートした際に、
障害の定義が先天的なもって生まれた他者との相違(機能障害や社会的不利)でなく、
関係性の中に生じる不都合さ(活動・参加の制限)のことに変わったのではないかと思います。
そもそも、障害の判定は僧侶ではなく医師や福祉相談所の判定員がするものなので、坊さんが障害の有無を決めつける立場にはありません。
娑婆の施策は本人の持ってる特性に焦点を当てての制度設計になりますが、それ以外の部分も含めた人間としての目線で以て考えるのが僧侶の視点だと思います。
私もかつての職場で一緒だった知的障がい者の葬儀に何回か参列した際、障害者手帳を持っているからといって法名や戒名がなかったということはなく、皆、仏弟子としての葬儀で看送られていました。(天理教と神道の方もいらっしゃったかな)
仏典の拠り所を探すまでの場つなぎと思い、思うところをつらつら書いて申し訳ありませんが、何かの参考になれば幸いです。
昔のインドでは身体に障害のある方に対し根欠という言い方をされていたようです。
ですが、根欠が差別の種にならないと言い切っているお経の注釈書もあります。
直接知的障害を指しているわけではありませんが、知的障害も身体障害の一つという捉え方が可能なら、知的障害にも当てはまるかと思います。
一切衆生悉有仏性
マイカ様
まず過去問にも同様に障害者と仏教について聞かれていますが、実生活で同様な方々と接する機会があるからの質問でしょうか?宜しければお答え頂ければと思います。
さて今回の質問への拙僧の見解です。
約2500年前、お釈迦様がこの世界で悟りを開かれ仏陀となって説法をされてのち、最初は口伝、そして文字・彫刻・絵画、様々な方法で伝承布教されてきました。
その過程で目の見えない人には口伝、耳が聴こえない或いは文字の読めない人には絵や彫刻そして仏像等の表現で仏法を伝えてきました。
そこには
「一切衆生悉有仏性」
[生きとし 生けるものは,すべて仏陀になる可能性をもっている]
「俱会一処」
[必ず一つの処(お浄土)でともに会う事が出来る]
などの教えを何とか伝えようとした先人の仏教徒の想いと実践の歴史があります。
知的理解力が一般より弱いからと言って、仏法が届かない事は絶対にありません。
今でも各地の僧侶が、その様な方々の輪の中に入って様々な方法を用い仏法を届けています。その想いがその心身に届いた時、既に仏教徒・仏弟子であるのです。
マイカ様自身、ご自分の生き方を見つめる必要性を感じているのなら、このサイトに質問される他に、是非お近くのお寺で説法をお聴聞し、可能であればあなた自身の疑問・悩みを僧侶にぶつけてみて下さい。モヤモヤしたものがハッキリ観えてきますヨ!
浄土真宗のお寺では毎日どこかでご法話が聴聞出来ます。
下記サイトで検索して、是非近くのお寺でお聴聞してみて下さい。殆どは無料で予約も要りません。
『浄土真宗の法話案内』
http://shinshuhouwa.info/
〇追伸
御礼有り難しです!
「僧侶に疑問をぶつける、、現実にお寺にいってそういうことができるのでしょうか?」との質問!
大阪でしたら、上記法話検索で調べてもわかる通り、多くの法座があります。法話後に主催側の許可や時間さえあれば、控室で個人的な質問・相談は可能です。布教使さんも喜ばれると思いますヨ!
自分の事を知るのが仏教
(^<^)ソフトに申し上げますが、いち早く、ご自分の事を問題にされることです。
ソトボリー(外堀)ばっかり埋めても意味がありません。自分のウチボリ―(内堀)が満たされることを仏教に要求することが、あなたが本当に仏教に出会う事。あなたにとっての仏への道、安らぎへの道、仏の教えに触れる機会の始まりでごんす。
知的障害を持たれる方を「問題にしている」のは誰でしょう?
ああ、ワタシが問題にしているんだなぁ、と気づいてみましょう。
そして、その「何か・誰か・外の事・疑問に思ったこと・相手・自分」を問題にするその自己をこそ問題にして、自己がどうあれば安楽なのかを真剣に求めるのが仏道なのです。
それを求めずして、人の事、外の事をお求めになられても、あなたの安心は得られないと思います。
坐禅会に、質問に来られる方々の4割は、外の事ばかりを問題にして問いかけます。
それでは、自分に目が向かないから、本人の救いは一向に始まらない。
自分をこそ本当は何とかしたいと思っているのではないでしょうか。
私どもはあなたの顔も、名前も、住所も知りようがありません。
秘密は守秘義務によって守られていますから、あなた自身の事を聞いてみましょう。(^<^)
何か気づかれることがありましたら、またご質問ください。
仏教は、ちゃんと全ての人を救う力を持っています。
どんなマイノリティーの方でも、私でもあなたも救われることが、仏教です。
たとえ、不条理、思い通りにならないことがこの世にあっても、それが本人にとって問題でなければ、他人様が問題にしても仕方ない事もあります。
一日も早く、自分の思いから自由になってください。
質問者からのお礼
まず皆様にお詫びと御礼を申し上げます。家庭の事情がありお返事ができない状況にありました。ご丁寧に書いていただいたのに無視してしまった形になり本当に大変失礼を致しました。
たいえんちょうさま
しゅりはんだか、のお話、とてもこころに響きました。障害というものは仰るとおり「関係性のなかに生じる人為的な不都合」、なのかもしれません。活動や参加の「制限」、を決める社会が、障害をつくっている。
そのひとを制限する枠組みこそがそのひとを障害者にしている。機能障害、生まれ持った時にもっている力は私たちはみな違うから。そこに普通なんてないですものね。そして障害者はこころで感じていますという言葉、感動しました。とかく障害者という言葉で別の存在のように片付けられてしまうことが間違っているのです。それに気づかせていただいて本当にありがとうございます!
中村太釈さま
>重度の精神・知的障害者は私たちと違うものさしで考えているので、仏教ととなり得るのか?という質問ですね。
彼らのちからを疑うのではなくて、逆に仏教というものが彼らを差別するか、という意味で書きました。悟るということが修行を必要とするものであれば物理的にそれができない場合どういう仏教の生き方が彼らに与えられているのかなと。次男さんの、「こころで受け入れていく、感じていく」ちから、それは仰るとおりまさに私達が逆に見習わなければいけないところなのかもしれません。障害者と呼ばれるひとたちがお寺や仏教に居場所をみつけることはできるのか、それがいつも気になっていました。悟る方法はたくさんあって、彼らなりに違う世界を理解していること、を忘れてはいけないことに気づかせていただいて本当にありがとうございます。
大熊範隆さま
そうですね、私の周りには障害を持った方がいます。彼らは身体的な問題から家からでられずお寺にいっても手をあわせることもできないひともいます。有り難い経典を読めたり理解できれば救われることもあるかもしれない中で、彼らがどのように仏教に関わることができるのかがいつも気になっていました。そしてお寺にとっても彼らの居場所というものはあるのかどうか。仏性はすべてのものにあると、それは理論的にはわかっていても、現実社会での彼らの存在はどのように「同じ人間」として受け入れられているのか。それが知りたかったのです。仏法が、僧侶などを通してこころにとどいたとき、概に仏教徒、これには気づきませんでした。そういう仏教のありかたもありえるのですね。本人の意思とは別に。私自身、そうですね、お寺というものは外国の教会とは違ってどうやっていくものかわからずに、遠巻きに見ていた部分があります。僧侶に疑問をぶつける、、現実にお寺にいってそういうことができるのでしょうか?(すみません初歩的な質問ですがどのように個人的に関わっていけるものなのかがわかりませんでした)少し勉強してみます。本当にご丁寧なご説明をありがとうございました。たくさん考えることがまたでてきました。
丹下覚元さま
暖かいお言葉をありがとうございます。どんなひとでも救われる、という言葉に思わず笑顔になってしまいます。仏教は、他の宗教よりもはるかにそういう意味ではいまを生きるために必要なことを教えてくれるものなのですね。仏教徒というものの意味に、どのようにあることが仏教徒で、障害者にはどのような可能性があるのか、というのを知りたかったのです。またなにかわからないことがありましたらご相談させていただきたいと思います。感謝をこめて。


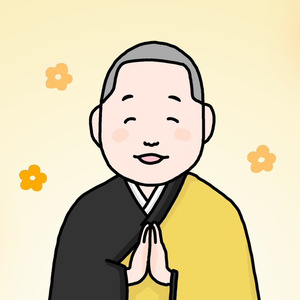

 特別な準備や、上手に話すことは必要ありません。
このオンライン相談の時間は、あなたのために差し出された時間です。
話すことだけが人生の目的ではありません。
言葉が浮かばないときは、
ただ呼吸に耳を澄ませる時間として過ごしていただいても構いません。
日常の中で受けている外からの抑圧やストレスから、
ひととき身を離れるための「避難の時間」として
この場を使っていただくこともできます。
僧侶である私は、何かを答える人というより、
あなたがこの時間を安心して過ごせるよう、
静かに同席する存在でありたいと考えています。
話がまとまらなくても、途中で止まっても大丈夫です。
この時間が、あなたのペースを取り戻すきっかけになれば幸いです。
なんまんだぶつ。
特別な準備や、上手に話すことは必要ありません。
このオンライン相談の時間は、あなたのために差し出された時間です。
話すことだけが人生の目的ではありません。
言葉が浮かばないときは、
ただ呼吸に耳を澄ませる時間として過ごしていただいても構いません。
日常の中で受けている外からの抑圧やストレスから、
ひととき身を離れるための「避難の時間」として
この場を使っていただくこともできます。
僧侶である私は、何かを答える人というより、
あなたがこの時間を安心して過ごせるよう、
静かに同席する存在でありたいと考えています。
話がまとまらなくても、途中で止まっても大丈夫です。
この時間が、あなたのペースを取り戻すきっかけになれば幸いです。
なんまんだぶつ。





