祖母を亡くした母の支えになるには
先日、ふるさとに住む祖母を亡くしました。
離れて暮らす私は、祖母が入院してから看病に通う母の話をきくことで支えになりたいと、できるだけ連絡を取り合っていました。
今のうちに見舞いに来て欲しいとのことで病床を訪ねてから、2週間ほどで祖母は亡くなりました。
入院してから数ヶ月もなく、母は最期は仕事を休み、泊まり込んでいました。
訃報を受けて、遠路を駆け付けました。
お葬式が済むまでに、母の深い悲しみを何度も目の当たりにしました。
私自身は、祖母とのお別れを、これからは心の中で思い、節目節目に供養しようと受け止めているつもりです。
しかし、母の哀しみは想像以上で、葬儀後徐々に日常生活に戻った私も、母の心を想うと胸が張り裂けそうです。
私にとっては生まれた時からおばあちゃんだった祖母も、母にとっては老いていったお母さんであった、という違いなのでしょうか。
一緒に祖母を供養して行こうねと伝えたいので、初盆にも帰る予定でいます。
私は、母にどのように寄り添っていけば支えになれるでしょうか。
お坊さんからの回答 4件
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
優しい流れ、繋がりを大切にして下さい
“私は、母にどのように寄り添っていけば支えになれるでしょうか。”
という
サリーちゃんさんの想いが
何よりも寄り添い、支えになるのではないかと思います。
今までのように
話を聞くこと
できるだけ連絡すること
一緒に供養していきたいと伝えること
“私は、母にどのように寄り添っていけば支えになれるでしょうか。”
という問いを持つことが
寄り添い、支えになるのではないでしょうか
サリーちゃんさんの
お母様を想う気持ちは
お母様との関わりからいただいたものだと思います。
お母様の深い悲しみは
お母様(祖母)との関わりからいただいたものだと思います。
サリーちゃんさんは
想い想われる優しい繋がり
流れの中にいるのだと思います。
その優しい流れ、繋がりを大切にして下さい
供養は恩を返すこと
サリーちゃん、はじめまして。
徳島県の法話と天井絵の寺 觀音寺 中村太釈です。
サリーちゃんの祖母を亡くされたとのこと。寂しくなりましたね。お悔やみ申し上げます。
さて、サリーちゃんが心配されているお母さまのことです。病床にあったとしても、お母さまはおばあさんのお世話することが生きがいとなっていのでしょう。お祖母ちゃんが亡くなった今、お母さんの生きがいも一緒に無くなったような気がして、喪失感に苛まれているのではないでしょうか。
サリーちゃんも節目節目に供養していきたいと考えておられるようですね。亡くなった親族を供養することは、恩を返していくことです。お母さまがお祖母ちゃんのお世話ができた恩を、供養として返していく日が来たのです。
通夜・葬式などは淡々と過ぎていきますが、亡くなったという喪失感は後から押し寄せてきます。寄せては返す波のように悲しみがやってきますが、やがて波は静まっていきます。
サリーちゃんの供養の心がお母さまの支えになると思います。
供養をしていく中で悲しみが癒やされますように。
浄土での再開を想い。。。。。。
「 愛別離苦 」大切な方と離れる事は、辛く苦しいです。
どうぞ気に留めて、寄り添ってあげてください。
難しい事は、必要ないです。
こまめに連絡をとってあげるとか。。。。。
人間は、身体の寿命が、あり、誰もが、必ず終わりが来ます。
でも、命 の終わりは無いと言います。
『 人間は、死なない 」と、私は縁ある、お葬式、法事でお話しをいたします。
(宗派により解釈は違いますが。。。。。)
私共のに、寿命が尽きた時にまた、かならず再開出来ます。
いつの日か、再開する事を楽しみに出来る日が訪れるはずです。
居てあげる事
「居る」
ということは、ただ、居るばかりではありません。
居る事によって、ものすごく力になることです。ただ居るだけでも人間、様々な事をお互いにしているのです。
私も今、まだ小さな子供が足もとに夜の十時四十五分を越えますが、居てくれているだけで、ものすごく安心感があるものなのです。
親御さんの死というものは、人間いつか必ず、諦めがつくものです。
悲しい時には悲しみに徹することが一番良いのです。
何もしなくても、居ることで十分それはしていることなのです。
共感、同調、ささえ、助けになってあげてください。
質問者からのお礼
お言葉を下さったお坊さま、ありがとうございます。
とても自分には抱えきれないのではないかと悩んでいましたが、そのまま受け止めて問い続けること、そばに居たいと思っていることを伝え、実行するだけでも良いと言っていただけて背筋が伸びました。
私にこれからできることがあり、それを祖母が教えてくれたのだと思って母の支えになっていきたいと思います。
また、檀家になっているお寺さまにも、初盆にはゆっくり説法をいただけると思うので、その時にまた自分の心を見つめ直してみようと思います。



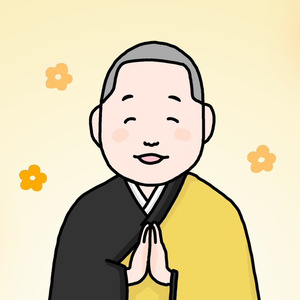


 お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00
お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00




