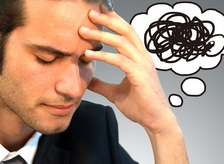母親の死と未だに向き合えません
母の三回忌を昨年秋に迎えました。
未だに母の死に向き合えず、後悔の念ばかりが出てきます。
母は癌を再発し、抗がん剤治療を続けていました。
その間に鬱から認知症を発症し、父親の老々介護だったこともあり、精神科に入院し、後、施設にて過ごしていました。
私が幼子の育児で大変だろうからという理由で、私には『大丈夫。心配するな』と常に言っていた両親でした。
姉夫婦から事後報告を受けるのみでした。
看護や介護に何も関わることなく、孫を逢わせに短時間だけ行くだけでの私で良かったのか。
『家にいつ帰れるの?』『もうすぐ帰るんだ』と自宅で過ごすことを楽しみにしていた母だったのに、父親の精神面や身体面から帰宅させなかったことが良かったのか。
子供が親を看護・介護することは当然なのにそれをしなかった私を怨んでいないか。
なんで私が最後まで寄り添ってあげなかったんだろうと悔しさでいっぱいです。
母の死ときちんと向き合うための心の整理の仕方や気持ちの切り替え方を教えて頂けると嬉しいです。
よろしくお願い致します。
お坊さんからの回答 2件
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
「大丈夫。心配するな」
まずはお悔み申し上げます。
確かに親の介護は当然という気持ちは理解できます。
しかし、幼子をかかえて、介護をやっていくなんて、とうてい無理なはなしです。
ヘルパーさんにお任せする以外方法はありません。
お母さんは、幼子をかかえたあなたに対し何も求めていません。
あなたに負担をかければ、孫にも、さらに家庭にも負担がかかる・・・・・
そんなこと、おかあさんが思う訳ないでしょう。
最後まで寄り添いたい気持ちは分かりますが、ゆりさんの元気な顔や、お孫さんの顔を見せるだけで、おかあさんは幸せだったと思いますよ。
また、帰宅は実現できませんでしたが、常に希望を持たれて亡くなられたのですから、ゆりさんは何も悪くありません。
そんなこと書いてたら「大丈夫。心配するな」って声が今にも聞こえて来そうです。
おかあさんは、ゆりさんの中で生きてらっしゃいます。
これからは、あなたがおかあさんにならなければいけません。
おかあさんから聞いた言葉、しぐさ、料理など、おかあさんを手本として、お子様を育て生きて下さい。
この生き方が、おかあさんの夢を実現することになると、私は思いました。
あなたが悲しむより、私を母として敬って供養しておくれ、と。
「母は今頃、こうしているのではないか。」
「母が生きていればこうするべきだったのではないか。」
「母はおそらく私にこうしてほしかったのではないか。」
これらの思いは❝誰が❞やっておられることでしょう。
どこでやっておられる事でしょう。
そして不安な思いが生じて苦しむ箇所は誰の何処の中でやっていることでしょうか。
そして、その思いは誰の上で生じて、誰が展開させてきたものでしょうか。
全部、あなたの中なのです。
厳密に言えば、あなたの中❝だけ❞でのことなのです。
あなたの中でだけ、そう苦しく感じられてしまう事なのです。
おそらくごお姉さん夫婦とあなたとは異なる感情であろうことは、なんとなくあなたも想像がつくことでありましょう。
「お母さんと向き合う」という事は、【自分の中の「母はきっとこうであろう」というわたくしの思いを一度手放す】必要があるのです。
わたくしを離れてただの人間になる事。
葬儀や法事などの儀式をするという事は形式やしきたりではないのです。
あなたがあなたの中の「私は」「私が」という❝わたくし❞という私情を捨て、公私も離れた大いなる公である「無私への帰郷」が大切なのです。
だから司祭、司式者という第三者を招いて、お互い公平おおやけな立場で「わたくし」ずることなく、供養をするのです。
それが亡きお母さんに対して尊厳を持たせて、わたしは私はという私情を捨ててお母さんに向き合うという事なのです。
これは喩えですが、あなたのお子さんやご主人のお誕生日を迎える時、たまたま、あなたが海外出張などで、誕生日の当日家にいてあげられなかったとします。
それがあらかじめ分かっていたので、相手の為を想って、ものすごーく時間と労力をかけて、自分なりに最高のものを厳選して買ってあげて送ったとします。
所が相手が望んでいたことは、一緒にいてくれることであったとします。
それは、実は相手に向き合っていないという事である、ということはお分かりいただけると思います。
亡くなった方に対してでも同じなのです。
本当のお母さんは、あなたの「うちの母はきっとこうしてほしいに違いない」ということとは別なのです。
供養の場に参列するという事は、真剣になるという事です。
人は物事に真剣に向き合う時には「私情」はありません。
お母さんの「大丈夫、心配するな。」はあなたに向けられた素敵なご遺言ですね。




 お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00
お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00