仏壇を前にしての悩み
これから軽め・重め問わず、色々な事を質問していきたいので、どうぞよろしくお願いします。
私はぶっちゃけ寺というTV番組を、深夜枠のときから見だして、仏教や寺との付き合いに興味を持ちました。
その影響でリビングにある仏壇の前に、ちょくちょく気が向いたとき、座るようになりました。
しかし、私の家は日蓮宗ですが、いざ仏壇を前にすると、いろいろ悩みがあります。
1,正しい作法を知らない。
お鈴の仕方。
南無妙法蓮華経は何回?
他に仏壇で唱えるべきお経。
その順番など。
2,日蓮宗では南無妙法蓮華経と唱えましょうと言っているが、意味も分からず唱えることに疑問。
本のタイトルを唱えて、本の内容は知らないのは滑稽さを感じる(法華経が、今を生きることの大切さを説いている、というのは何となく知っている)
3,家族はこういうことに無頓着、皆がテレビ見ている中、仏壇の前に座って南無妙法蓮華経と唱えると、かなり恥ずかしい気持ちになる。
20代一般人の自分が、仮に熱心に仏壇でお勤めしていたら、ちょっとヤバイ奴だと思う。自分でも友達にそういう人がいたらヤバイと思う。
など、単なる疑問や、体裁に関しての悩みが多いです。
最初は、勝手がわからずに南無妙法蓮華経と、唱えてました。
ですが今では恥ずかしさや、よくわからないまま南無妙法蓮華経と唱えることに、モヤモヤした気分になることから、一人の時に、線香一本上げて、チーンして、手をさっと合わせて、逃げるように後にして終わりです。
仏教をヤバイ宗教とは思わないですが、一般人が、特に若い人が、少しでも宗教に熱心だと、ヤバイ奴とみなされる日本社会の影響だと思います。
信者という言葉自体が、現代では負のイメージですし。
どうすればいいのか、どう考えたらいいのか。
まとまりのない質問文ですが、宜しければお答えよろしくお願いします。
お坊さんからの回答 3件
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
他宗派の者ですが
私は他の宗派の者で、あくまで個人的意見ですが、
南無妙法蓮華経は、南無三宝と同じ意味と思ってもよいのでは。
教えたまえる仏・説きたまえる法(教え)・伝えたまえる僧の三つを尊敬します、という意味。
名前には、イメージがついてきます。
名前を念じるときにはイメージも念じるので、心の善いイメージトレーニングになるのです。
思いが込められています
竹丸さん、はじめまして。
徳島県の法話と天井絵の寺、観音寺の中村太釈です。
ぶっちゃけ寺から仏教に興味を持ったのですね。有り難しです。
宗派を問わずお題目には祖師(宗派を開いた人)の思いが込められています。日蓮上人は南無妙法蓮華経にどのような思いを込めたのでしょうか。竹丸さんが調べてみてください。
なお、仏教に興味がある人はヤバいやつではないと思います。知的でカッコイいいと思いますがいかがでしょうか?ぶっちゃけ寺に出演しているお坊さんはカッコイいいですね。
音無きお題目を唱え(念じ)、行ってみてください。
坐禅は言葉なき念仏。
念仏は言葉のある坐禅。
念仏せられた心こそ坐禅 阿字観 止観であり坐禅 阿字観 止観せられた心こそ念仏が行ぜられた心といえます。
言葉、行の違いこそあれど目指す心はみな一心。
妙法蓮華経もまた、その念仏・坐禅せられた心から眺めた世界観。
お題目はその一切を内包する最上のお唱えの言葉。
そこに言葉が音とあるなしにこだわらず念ずるだけでもよいでしょう。
法に上下優劣はありません。みな釈迦の悟りの一心をあらわすものです。
私ども禅宗でも妙法蓮華経はお唱えします。
妙法蓮華なる行、妙法蓮華なる心を探求します。
どのような心が、妙法たる心と言えましょう。
それを探求すること、行為する事も、題目を唱える事に等しい行為です。
このhasunohaを立ち上げられた方や僧侶の一行一行の行為も、一言一言の回答もまた妙法蓮華の葉の一葉一枚、言の葉、コトノハ、hasunohaなのです。
言葉、好意こそ異なれど、みな導かんとする処はみな一心ではありませんか。
その言の葉を通じて、あなたが妙法蓮華なる心に目覚めて頂くことを祈念申し上げるばかりです。
声を出すことができない人は心の中で念じます。
あなたは理知的な人だから、表面的な事だけで、道理が分からないと、実行なされないと思います。では、かりにお経やお題目を読むこと、唱えることができなければ、それを実生活で「行じて」みてはいかがでしょうか。
知人の日蓮宗の僧侶は、お題目を唱えることから、生きたお題目を行ずることに目覚められました。活動や、実践です。
お経は、唱えるばかりがお経ではありません。
たとえばレシピは声に出して読むものではありません。
調理されることが無ければいけません。
さらには、命の尊さに目覚めなければいけません。
楽譜も読むものというより、演奏するものです。
ただ機械的に演奏すればいいかといえば、そうではありません。
そこに心、魂、ハートが無ければ音❝楽❞にはなりません。
演奏する手、声を失った人でも、人を喜ばせ、感動させる力は失われません。
お経は、仏様の心のありようが説かれた、解説書、説明書、レシピ、楽譜、マニュアル本とも言えます。
よくよく念ぜられ、熟慮され、行いとして、心のありかたとして、具現化されてゆくものなのです。お寺に行って生きたお経を説いてくれる僧侶を探してみてください。
質問者からのお礼
願誉浄史さん、ご回答ありがとうございます。
確かに後半は、何も考えず唱えていたと思います。
家族がいる中で、一人だけやっている自分を恥ずかしいと思い、早口でぼそぼそと唱えていました。
法華経の詳しい内容を知らなくても、南無(尊敬)の心を中心にイメージでもいいから、深呼吸してそれからゆっくり唱えてみようと思います。
追記、願誉浄史さん
早速実践しようと思ったら、母からついでに仏壇掃除しろと言われて、空拭き掃除しました。
その後、仏壇前に座って、深呼吸して目を開けると、本尊と先祖の位牌が、いつもと違う感覚で目に映りました。
「あぁ、この人たちがいたから、今俺がいるんだな」、「今まで下を向いたり、ボーっとして唱えていたんだな」とか思いました。
ちょっと良い経験をしました。ありがとうございます。
中村太釈さん 、ご回答ありがとうございます。
私の拙い知識の中では、今生きている現世が大事だから、南無妙法蓮華経と唱えるよう、日蓮さんは訴えたと認識してます。
そのうち、露の団姫さんの『法華経が好き!』を買おうと、思っています。
仏教の知識があるのは、カッコいいと思います。
ただ、小難しい部分はすぐに忘れてしまって…(八正道とかすぐ抜ける、)
知識もあまりないまま、南無妙法蓮華経とか南無阿弥陀仏とか、唱え続けたりるのは、お年寄り以外は、現代では引いた目で見られるじゃないかと、思うんです。
・仏教の知識←カッコいい
・ただ手を合わせる←日本人の普通の感覚
・一人仏壇の前で黙々と唱える若者(自分)←ヤバイ人じゃないか
と。仏教を理解するのは難しいから、とりあえず南無妙法蓮華経と唱えようと思い、興味を持ち、急にやっていた自分を振り返った際、一人仏壇の前で唱える自分をヤバイ、と考えてしまったんです。
ぶっちゃけ寺のお坊さんは、深夜メンバーからの方は顔と名前が一致します。
カッコイいい人もいますが、ウチの日蓮宗のあのお坊さん(いらっしゃ、かつ丼!)はどうでしょう。
笑顔のステキな方ですけどね(笑)
丹下覚元さん 、ご回答ありがとうございます。
うまく考えがまとまらず、次の日と思っていたら、ズルズルと遅くなりました。
すみません。
結局うまく言葉にはできないので、思った通りに書きますが…。
実践することは大事だと思います。
特に、料理や音楽の話は共感しました。
ただ、「言うは易し、行うは難しなんだよなぁ~」とも率直に読んだ際、思いました。
私はぶっちゃけ寺を見て、浄土真宗のお坊さんが話された、ただただ阿弥陀様にすがる的な考えから、仏壇前に座るようになりました。
辛い状況から逃げたかったのです。
無力感を感じていた自分は、南無妙法蓮華経と唱えることですがるしかないと、考えてしまったのです。
丹下覚元さんのお話は、私の心にチクリとくるものでした。
はたして実践できるものなのか不安ですが、やれる範囲で、 自分の心が幸せになるような善い行いをしていきたいです。
すみません、ネガティブで…。
取り繕って書くよりも、本音で書く方が良いと思い、「全く…」と思われるかもしれませんが、このように書かせていただきました。



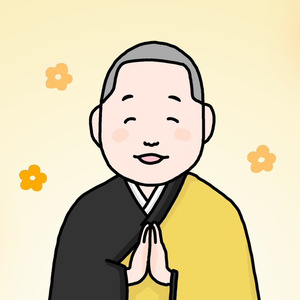

 お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00
お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00




