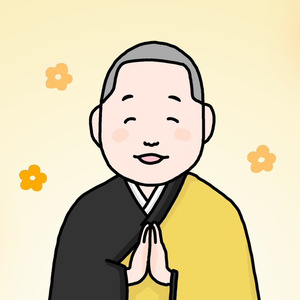母の死を乗り越えられていないのでしょうか
私は数年前に母を突然亡くしてしまいました。亡くなったとわかった時は信じられない、受け入れられないという気持ちで、それから時間が経つにつれて少しずつその気持ちや寂しさ、悲しさを自分なりに克服出来たつもりでした。
でも、今も時々思い出して寂しくなったり、家族と意見が合わず喧嘩した時に「お母さんがいてくれたら私の気持ちをわかってくれたのかな…」と考えて悲しくなったりします。
また母の死が本当に突然だったこともあり「人はいつ死ぬかわからない」という事実を改めて突きつけられたようで、それ以来家族や友達、恋人が死んでしまったらどうしようとふとした時に不安で仕方なくなります。例えば恋人が仕事で遠くに行くと聞いたら「行った先で事故や事件に巻き込まれたら…」とか、家族に車でどこかへ送ってもらう時に「私を送りに外出して、帰りに事故に遭ったら…」とか。
こういった不安やふとした時の寂しさ、悲しさがあるのは仕方ないことなのでしょうか?それとも、気持ちの持ちようで少しは軽減されると思われますか?
お坊さんからの回答 3件
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
お母様のおかげで諸行無常を学べた
お母様の死を乗り越えられていない、ということではないと思います。
○○さんが生きていてくれたら、などと考えることは、誰でも起こりえることでしょうし。
私は就職して1年目くらいに母を亡くしました。
その後、私は結婚して子供もできました。
たまに、母に孫を抱かせてあげたかった、子供をおばあちゃんと遊ばせてあげたかった、と妄想することはあります。(どちらかといえば楽しい妄想ですが。)
身内を亡くして諸行無常を痛感するのは、昔からよくある話ですから、それも普通です。
ただし、先日の質問同様に、いくら考えても仕方のない心配は「妄想」なので、繰り返し考えても何も「不安」以外は生まれませんね。
死ぬのが心配なら生命保険に入るとか、旅行に出た家族に安否確認をするとか、具体的な対策をするのは良いですが、むやみやたらに恐怖すると、人生が楽しくないから損ではないでしょうか。
怯えることより、目の前のテレビ
私たちはそうした中にいかされています。
その事実に気付かされたことは良かったことですね。
しかし、そこに怯えながら生きていては、意味がありません。そうしたことがあるかもしれない現実に生きていながらも、目の前のご飯を味わい。テレビを見て笑い、彼氏と楽しく会話するのです。
死というお別れが突然起こる可能性はありますが、人間とはそういうものだということを知っていれば、その時になったら考えればいいこと。お別れは寂しいけれど、いつか立ち直ることができます。
安心して今を生きてください。
寂しさと心配は別のもの
みんさん、はじめまして。
突然にお母さまを亡くされたとのこと。寂しくなられたことと思います。お悔やみ申し上げます。
さて、ふとしたことで亡くなったお母さまを思い出すことがあるのは自然なことです。故人を供養するのは、亡くなった人を忘れないためです。法事で故人を偲び、故人が生前に言っていたことを遺族で語り合うことは供養であり、遺族の癒しになります。
「人がいつ死ぬのか分からない」のは、すべての人が持っている宿命です。
みんさんが、他人を気にしてしまうのは心配しているだけです。それも、過剰な心配です。
亡くなる時が来るのは、誰にも分かりません。人が亡くなるのは誰のせいでもないのです。
故人を偲ぶ寂しさと、心配は別ものと考えましょう。
質問者からのお礼
ご回答ありがとうございます。
諸行無常という言葉は聞いたことがあったし、母自身も「今は元気だけど何があるかはわからないよね」というような話を時々していたのでわかっているつもりではいましたが、実際に母が亡くなってしまったことで気持ちがうまく整理出来なかったのかもしれません。
そればかり考えるのはやめて今を大事に、楽しく生きようと思います。




 ご相談時間は不定期なので、いくつかご都合を教えてください。
◆小学校教員もしています。子供、家族、ご自身のことお話をお聞きします。
◆禅のおかげで私も救われました。禅の教えを基に「思い通りにしたい」という自分の都合や価値観から生まれた思い込みをほぐしていくお手伝いをします。
◆仏教は人生を豊かにしてくれることを感じてくだされば嬉しく思います。
ご相談時間は不定期なので、いくつかご都合を教えてください。
◆小学校教員もしています。子供、家族、ご自身のことお話をお聞きします。
◆禅のおかげで私も救われました。禅の教えを基に「思い通りにしたい」という自分の都合や価値観から生まれた思い込みをほぐしていくお手伝いをします。
◆仏教は人生を豊かにしてくれることを感じてくだされば嬉しく思います。