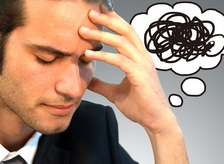友人関係など色々と学校に疲れてしまった
こんにちは。専門学校に通っているのですが、これが本当にやりたい事なのか分からなくなってしまったり、友人関係でトラブルがあり、みんなから見放されてしまったり、周りの目が怖くなったりしました。
最近、学校を休むことも多くなり、このままでは補講になったり、卒業できない可能性も出てきました。なので学校には行かないとって思って通っています。学校には、何とか行けてると言った感じなのですが、この精神的に辛い状況が3ヶ月以上続いており、限界をもう越しているのではないかと思っています。
しかし、学校を辞めたいと親に伝えるのも、今は片親なので、親に迷惑がかかってしまうし、学校を辞めてしまうとこの後の人生で、仕事に就くのが難しいのではと思ってしまいます。
先生にも相談しようと思ったのですが、やはり親に迷惑、将来が心配と思ってしまいます。
僕はこの先どう言った行動をとればいいのかアドバイスが欲しいです。
お坊さんからの回答 1件
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
学ぶということ自体を学ぶことですべてが学びだと気づける
まず、人間何を学ぶにしても「それ」だけを限定で学ぶというよりも「それ」でどう自分をより良い方向へ向かわせるかが大事だと思います。
❝何を学ぶかではなくそこで何をまなぶか❞(参学師の教えより)
今のあなたのその躓き・迷いだって学び。勉強。人生学問とみるべきです。
紆余曲折も失敗も「あー、あいつら嫌いだー。」と人間関係がうまくいかないのも学びです。「こりゃきつい、しんどい。」も良い授かりと考える事が大事なのです。
その躓き、アクシデント自体が出来事。キッカケ。あなたがああだこうだ悪く思う前に既にもともと無色透明の単なる出来事で、その出来事時代だって人によっては良いことと思えたり、悲しいと思えたりと、【無限の顔】【無限の価値】をもっているのです。
「それ」を学びつつ、「そこ」から何を学ぶか。
専門学校の学問もそうです。
あなたの今も苦しい状況も学びとすることが学生の道。学び活き、学び活かすことなのです。
だから、今その迷いが生じているまさに今のあなたのその心、その心情、その反応、そのこともそれも大きな学びの「機縁」なのです。
子供の頃から野球選手になりたかったけど残念な結果しか出せないプロ野球選手を喩えにいたします。せっかくプロになったものの野球選手だって結果を出せなければハラハラするでしょう。
野球が好きで野球をやりたくても結果が出せなかったり、自分より優れた人ばかりではやる気も失せるのが人間の心情でしょう。
ですが、優れた選手は「うしない」がそこで生じないと言います。
全てを学びとしてより良い方向へ向かわせ「転じて福」「好転」「善導」するのです。
あれは失敗だったとか「低評価」したり、
ああ、自分はダメだと「卑下」したり、
きっとこんなことが起こるに違いない…と「不安」な思いを起こして自分を追い込んだりすれば、ますますスランプに陥ります。いい結果も出せないかもしれません。
ですが、あなたはまだプロではない分、自由なのです。自由さを再認識する「学び」の道をゆくべきです。手にスキル・職をつけている学びの最中です。まだまだ可能性があり、学びの軌道修正ができる。そして、より良い選択肢やよりよい「道」を選ぶこともできるのです。
まだ安全地帯にいて、自由な動きができる段階なのです。引き返すこともできる。そして、この度の件を学びとして「上手に学ぶとはどういうことか」を学ぶのです。



 お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00
お悩み相談 080-2065ー9278(無料)お気持ちで浄財志納歓迎
月火水木金土日 8:00~21:00