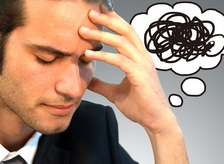祖母の死が悲しくない自分
初めて質問させていただきます。
数年前、母方の祖母が事故で亡くなりました。
幼い頃から、とても良くしてくれて大好きな祖母だったのですが、葬儀の際まったく悲しいという感情がわきませんでした。
周りの親戚や、私の兄弟たちは、みんな涙を流し悲しんでいるのに、私はその光景を他人事のように見ていました。
そんな自分が怖く、また祖母にたいして申し訳なく思っています。
私はこのまま普通に生活をおくっていってもいいのでしょうか。
お坊さんからの回答 3件
回答は各僧侶の個人的な意見で、仏教教義や宗派見解と異なることがあります。
多くの回答からあなたの人生を探してみてください。
実感があって涙が出る
悲しむことは義務ではありません、たとえ涙が出なかったとしても普通の生活を送ってはだめということになるかというとそんなことはありません
祖母に対する申し訳ないという気持ち、一応心の片隅でいいので持っておいてください
それは何故かと申しますと今はおそらく祖母が亡くなったという実感がKenさんの中に定着していないのかもしれません
今後ふとしたきっかけで祖母のことを思い出すことがあると思います、もしかするとその時にパズルのピースが丁度嵌まるようにあなたの心に実感が生まれるかもしれません、おそらくそのときあなたは涙を流せることと思います。
もしそうであったならそのときは遠慮なくそれまでの分思い切り泣けばいいのです、なので今泣かなくてもそれは悪いことではありません。
私も去年祖父を亡くしました。
3年ほど会ってはいませんでしたがお正月などに家に行くたびに家庭内麻雀でコミュニケーションしたり強面ではありましたが大好きでした。
亡くなってすぐは涙も出ず、私も複雑な心境でした、3年会って無かったからなのか、自分が冷たいだけなのか、そう考えていました。
今年の正月に3年ぶりに家に行きました、祖父は居ませんでした。
祖父の部屋は綺麗に片づけられ残っているのは祖母とあっちこっちに行った旅行のアルバムだけ、本当に綺麗なものでした。
庭いっぱいに育てていた祖父の趣味の植物もすべて無くなり、畑に変わっていました。
私も祖父と会わない間に僧侶となりましたので仏壇の前に座ってお経をあげようと思った瞬間、涙が溢れ出しました、そこで私は初めて祖父がお浄土へ往ったのだと実感したのです。
だからもし貴方が今後実感を伴って涙を流すときがくればそのときは思い切り泣いてください、涙はそのときはまで取っておいてください
涙は強要されるものではない
よく、最近卒業式や結婚式、葬儀などの場面や映画やドラマなどを見て「泣けた」といって得意げに話している人をテレビなどで目にします。
人前で「泣けた」ことを自慢のように言います。さも自分は良い人だろ。と言わんばかりに。
逆に涙を流さないと、つまらない、冷たい奴だといわれる。
変な話ですよね。
涙は自然と零れ落ちるもの。「泣ける」の言葉の裏には「泣きたい」が隠されていて、そこに意図的なものを感じます。
涙を流すかどうかは問題ではない。悲しく感じるかどうかは関係ない。ネバナラナイはない。ただ、そのようであったということにすぎないのです。
あなたがおばあちゃんから学んだことをあなたの人生の中でどのように生かすかということに尽きるのでしょう。それが供養です。
関わりの深さが涙の
直接的にあまり関わりがなかったならばいくら肉身と言えども涙が出ないものです。
ですが、いつかあなたにとって「祖母とは」を疑問にする日がやってきます。
自分をこの世に存在させてくれた人であることには変わりないものです。
人が人間性を追求すると、どうしても避けて通れないのが父母、祖父母、先祖。
その人たちと自分との関わり、関係性を通じて、あなたに生まれる心があります。
その心は、今は何も名づけません。
ですが、その心があると人間はあったかい。
愛にあふれる。優しくなれる。
そういう人間になれます。
そういう心がいっぱいある人がこのサイトを立ち上げました。
今日はライブドアのトップページにニュースとして紹介され、これからも多くの人の苦しみを救う、あったかい、やさしい心として、世の中にやさしさが広まっていく事でしょう。
あなたにもそういう心が眠っています。
手を合わせてもう一度、あばあちゃんとお母さんの関わり、お婆ちゃんとお父さんとの関わり、お婆ちゃんとあなたとの関わりを感じ取ってみてください。
ご冥福をお祈りいたしますとともに、あなたの中に「その心」が芽生え、いつか花咲きますように。
その為の心の栄養として、この蓮の葉、hasunohaで養分を吸収していってください。
合掌。




 ご相談時間は不定期なので、いくつかご都合を教えてください。
◆小学校教員もしています。子供、家族、ご自身のことお話をお聞きします。
◆禅のおかげで私も救われました。禅の教えを基に「思い通りにしたい」という自分の都合や価値観から生まれた思い込みをほぐしていくお手伝いをします。
◆仏教は人生を豊かにしてくれることを感じてくだされば嬉しく思います。
ご相談時間は不定期なので、いくつかご都合を教えてください。
◆小学校教員もしています。子供、家族、ご自身のことお話をお聞きします。
◆禅のおかげで私も救われました。禅の教えを基に「思い通りにしたい」という自分の都合や価値観から生まれた思い込みをほぐしていくお手伝いをします。
◆仏教は人生を豊かにしてくれることを感じてくだされば嬉しく思います。